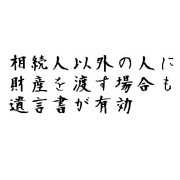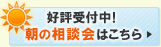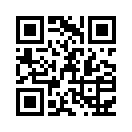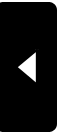にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年09月24日
遺言書の内容に納得してもらえるかわからない場合
先日、こんな相談がありました。
「せっかく作った遺言書、家族が納得してくれるかわからない。」
遺言書を作成しても、相続人がその通りの内容で納得してくれるかわからないこともありますね。
今回は、相続人が遺言書の内容に納得しなかった場合、どうなるかみてみましょう。
基本的には、遺言書の内容で相続人が納得いかない場合、相続人間で話し合いになります。
話し合いで相続人の全員が納得した場合は、遺産分割協議書というものを作成します。
ここで、話し合いで相続人が納得いかない場合、次に調停というものをします。
これは、家庭裁判所に申し立てをします。第三者(調停委員)が間に入って話し合いになります。
調停でも折り合いがつかない場合は、訴訟ということになります。

「せっかく作った遺言書、家族が納得してくれるかわからない。」
遺言書を作成しても、相続人がその通りの内容で納得してくれるかわからないこともありますね。
今回は、相続人が遺言書の内容に納得しなかった場合、どうなるかみてみましょう。
基本的には、遺言書の内容で相続人が納得いかない場合、相続人間で話し合いになります。
話し合いで相続人の全員が納得した場合は、遺産分割協議書というものを作成します。
ここで、話し合いで相続人が納得いかない場合、次に調停というものをします。
これは、家庭裁判所に申し立てをします。第三者(調停委員)が間に入って話し合いになります。
調停でも折り合いがつかない場合は、訴訟ということになります。

2010年09月22日
相続財産を渡したい人がいる場合
2010年09月20日
相続財産を渡したくない人がいる場合 その2
遺言書で、”分割割合の指定”や”廃除の指定”をすることが有効な手段の一つだと前回の記事でお伝えしました。
(前回の記事「相続財産を渡したくない人がいる場合」)
さらにこんな方法もあります。
”生命保険の受取人の指定”
です。
これは、相続人から遺留分の請求(※)にも対応できます。
例えば、相続人AさんとBさんがいるとします。
Bさんに相続財産を渡したくないと思った場合、保険の受取人をAさんに指定し、Bさんから遺留分の請求をされてもこの保険金で遺留分の請求にも対応することができます。
(※)遺留分の請求とは、相続人がもっている遺留分の主張をしてくることです。遺留分減殺請求といい、自己の遺留分の保全のための請求ともいいます。
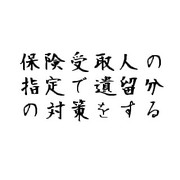
2010年09月17日
相続財産を渡したくない人がいる場合
状況によっては、ご自身の財産を相続させたくない人がいるということもあると思います。
実際に相続開始になる前に何かいい方法はないでしょうか?
実は、そんな時も遺言書が有効な手段の一つとなります。
遺言書で、”財産の分割割合の指定”をしたり”相続人の廃除の指定”ができるのです。
相続人AさんとBさんがいる場合、Aさんに8割、Bさんに2割などの分割割合の指定や、Bさんは相続人から廃除するということも遺言書で記載できます。
このように遺言書で指定した場合、付言事項で分割割合を指定した理由や廃除した理由を書くことが重要です。

実際に相続開始になる前に何かいい方法はないでしょうか?
実は、そんな時も遺言書が有効な手段の一つとなります。
遺言書で、”財産の分割割合の指定”をしたり”相続人の廃除の指定”ができるのです。
相続人AさんとBさんがいる場合、Aさんに8割、Bさんに2割などの分割割合の指定や、Bさんは相続人から廃除するということも遺言書で記載できます。
このように遺言書で指定した場合、付言事項で分割割合を指定した理由や廃除した理由を書くことが重要です。

2010年09月15日
相続の形態:相続放棄
民法上、相続の形態としては3種類あります。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
今回は、相続放棄のことについてみてみましょう。
民法第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
もともと相続人でなかった扱いになります。
これは、家庭裁判所に申立てをして受理されれば効力が生じます。
相続の放棄も、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなくてはいけません。
他にも以前の記事『遺留分の放棄と相続の放棄』でご紹介したとおり、
・相続開始前の放棄はできない
・放棄すると他人の相続分が増加する
・放棄すると相続の権利が失われる(遺留分もなくなる)
といった特徴があります。
相続を放棄したからといっても、自分のものと同様に相続財産を管理する義務は残っています。
(自己財産同一注意義務といいます。)

2010年09月13日
相続の形態:限定承認
民法上、相続の形態としては3種類あります。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
今回は、限定承認のことについてみてみましょう。
民法第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
”得た財産の限度”ですので、プラス分の資産の全部と考えるとわかりやすいです。
”債務及び遺贈を弁済すべきことを留保”ですので、払わなくてよいことになります。
つまり、ブラス分の資産の全部を超えたマイナスの資産は払わなくてよいということです。
例えば、
プラスの資産(現金+不動産で2000万円)
マイナスの資産(借金3000万円)
であった場合、プラスの資産から2000万円は返済し、残りのマイナスの資産1000万円は支払わなくてもよいことになります。
プラスの財産もあるし、マイナスの財産もあるけれども、どっちが多いのかわからない場合には、有効な手段です。
ただし、相続人が複数人いる場合は共同してしなくてはならないこと、家庭裁判所に戸籍や財産目録をもって申し立てすることなど単純承認より多少の手続きが必要となります。

・単純承認
・限定承認
・相続放棄
今回は、限定承認のことについてみてみましょう。
民法第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
”得た財産の限度”ですので、プラス分の資産の全部と考えるとわかりやすいです。
”債務及び遺贈を弁済すべきことを留保”ですので、払わなくてよいことになります。
つまり、ブラス分の資産の全部を超えたマイナスの資産は払わなくてよいということです。
例えば、
プラスの資産(現金+不動産で2000万円)
マイナスの資産(借金3000万円)
であった場合、プラスの資産から2000万円は返済し、残りのマイナスの資産1000万円は支払わなくてもよいことになります。
プラスの財産もあるし、マイナスの財産もあるけれども、どっちが多いのかわからない場合には、有効な手段です。
ただし、相続人が複数人いる場合は共同してしなくてはならないこと、家庭裁判所に戸籍や財産目録をもって申し立てすることなど単純承認より多少の手続きが必要となります。

2010年09月10日
相続の基本形:単純承認
前回、「相続が開始したらあなたはどうしますか?」での相続の形態をみてみましょう。
3ヶ月以内に相続形態の結論がでない場合は単純承認となるので、相続の形態の基本ともいえます。
民法第920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
”無限に”ですので、プラスの財産はもちろんマイナスの財産も全部相続することになります。
もちろんマイナスの財産が多ければ自分の財産をあてて弁済することになります。
しかし、マイナスの財産が多いときは困ってしまいますね。
続きは、次回にご紹介します。

3ヶ月以内に相続形態の結論がでない場合は単純承認となるので、相続の形態の基本ともいえます。
民法第920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
”無限に”ですので、プラスの財産はもちろんマイナスの財産も全部相続することになります。
もちろんマイナスの財産が多ければ自分の財産をあてて弁済することになります。
しかし、マイナスの財産が多いときは困ってしまいますね。
続きは、次回にご紹介します。

2010年09月08日
相続が開始したらあなたはどうしますか?
前回の「相続の放棄と遺留分の放棄」でも少しふれました相続についてみてみましょう。
民法上、相続の形態としては3種類あります。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内に3種類の中から1つを決めなくてはいけません。
3ヶ月以内に結論をださない場合は単純承認をしたものとみなされます。
長いようで短い3ヶ月ですので、注意が必要です。
対策として財産一覧表があると、相続手続きがスムーズになります。
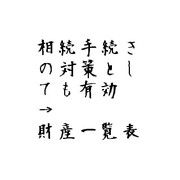
2010年09月06日
遺留分の放棄と相続の放棄
前回でてきた、「遺留分の放棄」。相続の放棄とは違いますが、簡単にまとめてみましょう。
『遺留分の放棄』
相続開始前でも放棄はできる
放棄しても他人の遺留分は増加しない
放棄しても相続の権利が失われない
『相続の放棄』
相続開始前の放棄はできない
放棄すると他人の相続分が増加する
放棄すると相続の権利が失われる(遺留分もなくなる)
並べてみると違いがよくわかりますね。

『遺留分の放棄』
相続開始前でも放棄はできる
放棄しても他人の遺留分は増加しない
放棄しても相続の権利が失われない
『相続の放棄』
相続開始前の放棄はできない
放棄すると他人の相続分が増加する
放棄すると相続の権利が失われる(遺留分もなくなる)
並べてみると違いがよくわかりますね。

2010年09月03日
遺留分の放棄
遺言書で特定の相続人に財産を相続させる場合、遺留分に配慮する必要があります。
(詳しくは、前回の記事「持っている農地(田・畑)を子に継がせる」参照)
では、その遺留分を放棄することはできるでしょうか?
答えは、できます。
相続人が複数人いても、全員でする必要はありません。相続人の1人だけ遺留分を放棄することもできます。
遺留分は相続する財産のうちの法律で保障された割合です。相続の権利とは違うので、遺留分を放棄しても相続する権利はなくなりません。

2010年09月01日
持っている農地(田・畑)を子に継がせる
前回の「特別に財産を残したい方がいる場合」の例として、子に農地を相続する場合を考えてみましょう。
農業を継がせるなど、土地を分割したくない場合などに有効です。
遺言書での文例
第○条 遺言者は、次の不動産を長男△△(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
所在 □□県□□市□□町□□
地番 ○○番地
地目 田
地積 ○○平方メートル
前回のとおり、遺留分の問題が残ることがありますので、遺言書にて何かしら配慮した内容を記載するのが望ましいでしょう。
第○条 前条の財産を相続したとき、長男△△は次の義務を負うこと。
妻△△を扶養し、その面倒をみること
長女に○○万円を支払うこと
遺留分に反する内容を記載しても無効にはなりませんが、相続人への配慮が必要になってきます。

農業を継がせるなど、土地を分割したくない場合などに有効です。
遺言書での文例
第○条 遺言者は、次の不動産を長男△△(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
所在 □□県□□市□□町□□
地番 ○○番地
地目 田
地積 ○○平方メートル
前回のとおり、遺留分の問題が残ることがありますので、遺言書にて何かしら配慮した内容を記載するのが望ましいでしょう。
第○条 前条の財産を相続したとき、長男△△は次の義務を負うこと。
妻△△を扶養し、その面倒をみること
長女に○○万円を支払うこと
遺留分に反する内容を記載しても無効にはなりませんが、相続人への配慮が必要になってきます。

2010年08月30日
美人粥で静岡を満喫っ♪
週末にいただいた噂の『美人粥』
さっそく食べちゃいましたっ。
風味がすごいですよ。上品なあじわい。口の中で静岡県が広がりますっ!
四の五のいわずに食べてみてっ!!!
夏バテしらずです。
http://surugayume.eshizuoka.jp/
http://blog.shizuokaonline.com/asten/2010/05/post_28.html


さっそく食べちゃいましたっ。
風味がすごいですよ。上品なあじわい。口の中で静岡県が広がりますっ!
四の五のいわずに食べてみてっ!!!
夏バテしらずです。
http://surugayume.eshizuoka.jp/
http://blog.shizuokaonline.com/asten/2010/05/post_28.html
2010年08月27日
特別に財産を残したい方がいる場合
例えば、「自分の老後の面倒を見てもらう」「ペットの面倒を見てもらいたい」など、
何かをしてもらうから多く財産を残したい場合がありますね。
1つの方法として、遺言書で指定する方法があります。
『○○に以下の財産を相続させる。』などと指定して遺言書を作成します。
ただし、遺留分に気をつけなければなりません。
遺留分を主張することができる人は、兄弟姉妹以外の相続人です。
配偶者、子、両親などが該当しますね。その割合は両親などの直系尊属のみが
相続人である場合は、3分の1。それ以外は2分の1です。
詳しくは、過去の記事「遺留分って何?」をご覧下さい。
2つめの方法として、贈与契約があります。
「無効な自筆証書遺言を有効にしたい場合」でもご紹介しました贈与契約です。
生前に財産を残したい方とお互いに確認し契約をすることで成立し、財産を残す
ことが出来ます。
ただし、この場合も気をつけることがあります。例えば老後の面倒を見ることが
契約の条件だった場合は、老後の面倒を見ていなかったとして、他の相続人
から契約の取消しが主張されることもあります。

何かをしてもらうから多く財産を残したい場合がありますね。
1つの方法として、遺言書で指定する方法があります。
『○○に以下の財産を相続させる。』などと指定して遺言書を作成します。
ただし、遺留分に気をつけなければなりません。
遺留分を主張することができる人は、兄弟姉妹以外の相続人です。
配偶者、子、両親などが該当しますね。その割合は両親などの直系尊属のみが
相続人である場合は、3分の1。それ以外は2分の1です。
詳しくは、過去の記事「遺留分って何?」をご覧下さい。
2つめの方法として、贈与契約があります。
「無効な自筆証書遺言を有効にしたい場合」でもご紹介しました贈与契約です。
生前に財産を残したい方とお互いに確認し契約をすることで成立し、財産を残す
ことが出来ます。
ただし、この場合も気をつけることがあります。例えば老後の面倒を見ることが
契約の条件だった場合は、老後の面倒を見ていなかったとして、他の相続人
から契約の取消しが主張されることもあります。

2010年08月25日
相続時精算課税方式
相続財産の分割を考えるとき、先に贈与したほうがいいのか、相続まで待ったほうがいいのかと考えることがあります。
そこで、今日は税金のお話。
相続税の控除で、「贈与税額控除」と「相続時精算課税」というものがあります。
「贈与税額控除」・・3年以内の贈与財産にかかった贈与税を相続税から控除するというもの
「相続時精算課税」・・贈与税を少なく払っておいて、相続税でその分を精算するというもの
どちらも先に払った税金分(贈与税)を相続税の時に控除するものです。
先に財産を渡すことで移転コストがかかりますが、名義がかわることで財産からの利益も渡すことが出来ます。
「相続時精算課税」については、対象者に制限(親65歳以上、子20歳以上)がありますが、控除の限度2,500万円なので、メリットが多い方がいるのではないでしょうか。(相続税の基礎控除は110万円)
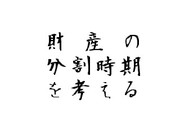
そこで、今日は税金のお話。
相続税の控除で、「贈与税額控除」と「相続時精算課税」というものがあります。
「贈与税額控除」・・3年以内の贈与財産にかかった贈与税を相続税から控除するというもの
「相続時精算課税」・・贈与税を少なく払っておいて、相続税でその分を精算するというもの
どちらも先に払った税金分(贈与税)を相続税の時に控除するものです。
先に財産を渡すことで移転コストがかかりますが、名義がかわることで財産からの利益も渡すことが出来ます。
「相続時精算課税」については、対象者に制限(親65歳以上、子20歳以上)がありますが、控除の限度2,500万円なので、メリットが多い方がいるのではないでしょうか。(相続税の基礎控除は110万円)
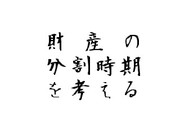
2010年08月23日
財産一覧表を作成するということ
前回のエンディングノートは簡易的な財産一覧表にもなるとご紹介しました。
では、財産一覧表を作成するメリットを考えて見ましょう。
・自分の財産を一覧にすることで財産の確認ができる。
・分割方法を考えることができる。
・相続の対策ができる。
・相続税がかかりそうかの判断ができる。
・相続税の対策ができる。
財産の内容の一例はこちらを参照。 ⇒ 「作成のポイント(財産一覧表)」
これからも、財産の変動はあると思いますが、現時点での一覧を作成してみるとご自身の財産を今後どのようにするべきか方向性がみえますね。

では、財産一覧表を作成するメリットを考えて見ましょう。
・自分の財産を一覧にすることで財産の確認ができる。
・分割方法を考えることができる。
・相続の対策ができる。
・相続税がかかりそうかの判断ができる。
・相続税の対策ができる。
財産の内容の一例はこちらを参照。 ⇒ 「作成のポイント(財産一覧表)」
これからも、財産の変動はあると思いますが、現時点での一覧を作成してみるとご自身の財産を今後どのようにするべきか方向性がみえますね。

2010年08月20日
エンディングノート<もしもの時に役立つノート>
コクヨS&T株式会社さんが、発売予定の「エンディングノート」。
エンディングノートとは、もしもの時に備えてノートにあらゆる情報を書き留めておきましょうというものです。
簡易的な財産一覧表といってもいいかもしれません。
ディスクケースがついていたり、WebサイトのIDを記入できたりもするようです。遺したい電子データも多いですからね。ちょっとした気配りに惹かれます。
http://www.kokuyo.co.jp/press/2010/08/1068.html
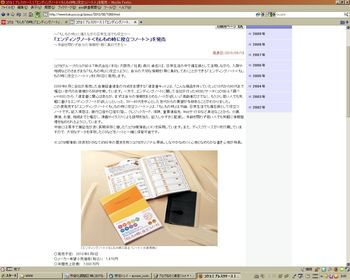
2010年08月18日
無効な自筆証書遺言を有効にしたい場合
自筆証書遺言では、ポイントとして次の4点があげられます。
・自書すること
・日付が記載されていること
・署名がされていること
・押印されていること
(この内容を取り上げた以前の記事はこちら)
自筆証書遺言は、この中のどれかが欠けると法律的に無効となってしまいます。
無効の場合、相続財産は共有となってしまいますが、遺言書と同じ分割の
方法で相続できる場合があります。
それは、”死因贈与契約”というものです。
お互いに話し合ってから相続財産の分割方法を指定している場合、
この死因贈与契約が成立する可能性があります。
ただし、それには条件があります。
・被相続人が「この財産を贈与しますよ。」という申込みの意思表示があること
・相続人が「その財産を贈与されることに承諾します。」という承諾の意思表示があること
・なにより死後に財産を贈与するという死因贈与であること
この条件を証明することで、死因贈与契約と認められ無効な遺言書と同じ割合で
財産を分割することができます。
民法上の契約では、「あげますよ」の意思表示(申込み)と「もらいますよ」の意思表示
(承諾)の合致があって初めて契約が成立します。この場合には、口頭であったとしても
証明できれば有効な契約となります。

・自書すること
・日付が記載されていること
・署名がされていること
・押印されていること
(この内容を取り上げた以前の記事はこちら)
自筆証書遺言は、この中のどれかが欠けると法律的に無効となってしまいます。
無効の場合、相続財産は共有となってしまいますが、遺言書と同じ分割の
方法で相続できる場合があります。
それは、”死因贈与契約”というものです。
お互いに話し合ってから相続財産の分割方法を指定している場合、
この死因贈与契約が成立する可能性があります。
ただし、それには条件があります。
・被相続人が「この財産を贈与しますよ。」という申込みの意思表示があること
・相続人が「その財産を贈与されることに承諾します。」という承諾の意思表示があること
・なにより死後に財産を贈与するという死因贈与であること
この条件を証明することで、死因贈与契約と認められ無効な遺言書と同じ割合で
財産を分割することができます。
民法上の契約では、「あげますよ」の意思表示(申込み)と「もらいますよ」の意思表示
(承諾)の合致があって初めて契約が成立します。この場合には、口頭であったとしても
証明できれば有効な契約となります。

2010年08月16日
便利サービス「e遺言.com」
便利な世の中になったものです。
法律的な効力がある遺言書ではありませんが、家族への想いを遺すにはお手軽なサービスといえるのではないでしょうか?
http://www.eyuigon.com/
デモ体験も出来て、試す価値有りです!

法律的な効力がある遺言書ではありませんが、家族への想いを遺すにはお手軽なサービスといえるのではないでしょうか?
http://www.eyuigon.com/
デモ体験も出来て、試す価値有りです!

2010年08月13日
iPhooooooneっ!
ついに手に入れましたっ!
思えば、iPhone熱が急上昇した北遠ブログ村での出来事から1ヶ月半で入手してしまいました^^;
設定、なかなか大変ですね。。。
分厚い取説ないんですね。。。
ちょくちょくカスタマイズしていきますよー

思えば、iPhone熱が急上昇した北遠ブログ村での出来事から1ヶ月半で入手してしまいました^^;
設定、なかなか大変ですね。。。
分厚い取説ないんですね。。。
ちょくちょくカスタマイズしていきますよー
タグ :iPhone
2010年08月11日
遺言書は誰の為にあるのか?
『遺言書』というと最近ではニュースでも聞くことが多くなってきていますが、
身近であるかといわれるとちょっと疑問が残るものではないでしょうか?
自分にはまだ必要ないと思われる方も少なくありません。
では、遺言書は誰の為にあると思いますか?
遺言書の役割として、亡くなった方の財産(遺産)の分割方法の指定があげられますね。
法律で遺産を分割する割合(法定相続分)が決まっているから自分が
何も言わなくても大丈夫と思う方もいるかもしれません。しかし、それが
上手くいかないから”争続”なんて言葉もあるのです。
法律で割合が決まっていますが、やっぱりご自身の財産の分割方法は、
ご自身で決めるのが一番です。
残された家族も、「本人がそう言うなら」と納得することも多いでしょう。
また、遺言書には付言事項といって、法律的な拘束力はありませんが
自由に内容を記載することもできます。
この付言事項で、分割方法を指定した理由であったり、残された家族への
気持ちを伝えることができます。
最後の意思表示として尊重することが多いため、一定の効力があるともいえます。
(以前の記事でも何度か取り上げました ⇒ 「付言事項」)
遺言書は、自分のためのものでもありますが、残された家族のためのものでもあるのです。

身近であるかといわれるとちょっと疑問が残るものではないでしょうか?
自分にはまだ必要ないと思われる方も少なくありません。
では、遺言書は誰の為にあると思いますか?
遺言書の役割として、亡くなった方の財産(遺産)の分割方法の指定があげられますね。
法律で遺産を分割する割合(法定相続分)が決まっているから自分が
何も言わなくても大丈夫と思う方もいるかもしれません。しかし、それが
上手くいかないから”争続”なんて言葉もあるのです。
法律で割合が決まっていますが、やっぱりご自身の財産の分割方法は、
ご自身で決めるのが一番です。
残された家族も、「本人がそう言うなら」と納得することも多いでしょう。
また、遺言書には付言事項といって、法律的な拘束力はありませんが
自由に内容を記載することもできます。
この付言事項で、分割方法を指定した理由であったり、残された家族への
気持ちを伝えることができます。
最後の意思表示として尊重することが多いため、一定の効力があるともいえます。
(以前の記事でも何度か取り上げました ⇒ 「付言事項」)
遺言書は、自分のためのものでもありますが、残された家族のためのものでもあるのです。